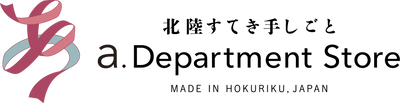福井県の7つの伝統工芸の中でも、歴史の長い越前和紙には一つの伝説があります。
伝説では、約1500年前(5世紀末)、後の継体天皇が越前地方を統治していたとされた頃、岡本川の上流に1人の女性が現れ、田畑の少ない五箇地区の土地に紙漉きの技術を丁寧に伝えたと言われています。喜んだ村人がその女性に名前を尋ねると、「この川上に住む者」とだけ答え、姿を消してしまいました。村人たちは、この女性を川上御前と尊び、紙祖(しそ・紙の始まりの元祖)の神様として、岡太神社にお祀りしました。

川上御前の謂れ
また、明治8年、紙幣寮抄紙局での新しい国産紙幣用紙の開発にあたり、越前五箇から紙漉き職人が募集されます。抄紙局でその紙漉き職人たちと現地の局員とで共に研究を重ね、現在のお札に繋がる紙幣用紙製造の基礎技術を築きました。そして、大正12年に川上御前の御分霊を祀りたいという抄紙部からの要望で数ある紙祖の中でも国家機関の印刷局に祀られることになり、日本の紙業界の守り神として、全国の和紙・洋紙業界から尊ばれる紙の神様となりました。
そのような川上御前=水波能賣神(みずはのめのかみ)が祀られている岡太神社は、大瀧神社と共に山の麓には里宮が置かれ、頂上に登ると奥の院があります。里宮の境内には、多くの杉、桜、ブナ、イチョウなどが天高く聳え、神聖な空気を感じることができます。和紙が貼られた灯籠や苔の生えた石畳や階段も厳かな社殿を引き立たせ、一度は訪
れてほしい場所です。

天高く成長する大木。澄み渡った空気が感じられます
また、川上御前は年2回奥の院から里に降りて来られるため、里の皆でお迎えして、お祭りを行います。特に5月3日〜5日に行われる「神と紙の祭り」は、県の無形民俗文化財にも指定されています。初日は「お下り」。白装束を着た男性たちが、空のお神輿を担ぎ、奥の院に上がり、川上御前をお迎えに行きます。4日は川上御前を歓迎する神事が行われ、最終日は「渡り神輿」、御身体を乗せた御神輿が五箇の街中を練り歩きます。

大瀧・岡太神社、里の宮の社殿

岡太神社奥の宮

御神輿を担いで、川上御前の御神体を奥の院から降ろしてきます。
この川上御前が紙漉きを教えてくださった1500年前から、その技をたくさんの人たちに伝え、受け継いだからこそ、今もなお、このような越前和紙の存在があります。川上御前の存在が、その時その時の職人さんたちの心を支え、里の人々を支え繋げ、幾年も幾年も職人一人一人に和紙を漉かせてきたのです。「和紙を漉く」。そう容易いものではなく、根気強く、真摯に取り組む姿勢が1500年もの歳月を紡いできたのだと思います。
今でも五箇地区ではたくさんの和紙漉きの工房が軒を連ねています。そこでしか作れないたくさんの越前和紙が存在します。工房によっては、和紙漉きなどの体験をさせていただくこともできます。体験を通じて、長い年月を経て紡がれた越前和紙を感じていただけると嬉しく思います。

五十嵐製紙さんでの墨流し体験。好きな色を組み合わせて模様を作ります。

墨流しでできた自分だけの越前和紙

ひっかけ技法で作るひよこ柄
漉いた和紙にみずしぶきで穴を開けたり柄をつけた後、先ほどのひっかけで作ったひよこを乗せてみました。

乾かして出来上がったひっかけ技法で作った越前和紙。思っていたよりもうまく柄が見えず、さすがに難しさを感じました!
やなせ和紙の皆様、ありがとうございました。
**
五十嵐郁子
1975年生。東京在住。エーデパディレクター。福井県越前市生まれ。日本女子大学卒。大学生の2人の娘の母。東京福井県人会理事。福井市応援隊サポーター。