去年あたりから、福井県出身の私なら、知っているだろうと
「年縞博物館に行ってみたいんだけど」「年縞博物館て素晴らしいんでしょ?」などと質問される機会が増えていました。
年縞というとなんのことだろうと考えてしまうようなちょっと難しげなもの。年縞博物館を調べてみたところ、地層のこと?あんまり興味ないかもしれないなあと思いつつ、私も先日「年縞博物館」へ行ってきました。
私たちが車で到着すると、自転車で来られた10名近くのグループが同時に到着し、どうして自転車???と疑問に思っている中、入館。
その自転車で来られたグループの方々と一緒にガイドをしてもらうことに。まずは、丸い小部屋に通され、椅子に座りました。周りをぐるりと囲む白い壁に映るほんの数分のプロジェクションマッピング!地層を深く入り込み長い年月を遡る旅。あっという間に私たちを年縞の虜にさせたのでした。
 小さい円柱型の部屋に通され、深い深い地層への旅が始まります!
小さい円柱型の部屋に通され、深い深い地層への旅が始まります!
年縞とは、「長い年月の間に湖沼などに堆積した層が描く特徴的な縞模様の湖底堆積物」のことで、1年に1層形成されます。

明るいところは冬に積もったところ、暗いところは夏に積もったところだそう。地層を横に展示しています。
三方五湖の一つ、水月湖は、奇跡の湖と呼ばれ、その年縞が美しい縞模様をしています。その理由として、直接流れ込む河川がないこと。湖底に生物が生存していないこと。時間が経過しても埋まらないことの3つが挙げられるそうです。その3つの要因により、年縞が形成される奇跡的で理想的な湖だそうです。さらに、1年に約0.7ミリ積もる地層が7万年分、1年も欠かすことなくあるのです。7万年の年縞があるのは、世界でもこの水月湖だけだそうです。


昔々の原始人の頭蓋骨。地層の成分と骨の成分を調べるとさまざまなことがわかってくるそう
7万年分もの地層がくりなす年縞は、さまざまなことを教えてくれるのだそう。例えば、地層に含まれる成分で、その年の気候や生存している動物、植物など。例えば、見つかった土器や骨などに含まれる炭素と年縞にある炭素の量などを見比べることで、いつの年代のものかが正確に解明できるそうです。また、地層に残る花粉の成分を調べることで、その時の気候などを調べることもできます。この年縞が世界水準のものさしと呼ばれ、これからもさまざまな分野の研究に役立てることや開発にも大きく関係していくことなども事細かく、展示されていました。

また、全国にある5000の美術館、博物館の中で第2回日本博物館協会賞を受賞し、日本No.1の博物館になったそうです。
人間1人が生きている年数の年縞は約たったの60ミリ。この年縞博物館に行き、遥かに長い年月、堆積した地層を見て、私は人生で初めて地球という壮大な浪漫(初めて使う言葉かも笑)を見たような気がします。
細長い建物は、その地層7万年分を横長に展示するためのもの。博物館を出て、振り返って建物を見たとき、感動と共に知りました。また、自転車で訪れていたグループは、三方五湖をサイクリングして回っていたようです。三方五湖を自転車で堪能して、古代の風景を想像しながら楽しむ旅を次回はして見たいものです。
**
五十嵐郁子
1975年生。東京在住。エーデパディレクター。福井県越前市生まれ。日本女子大学卒。大学生の2人の娘の母。東京福井県人会理事。
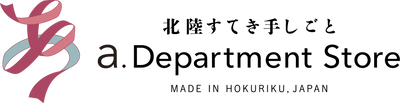



 若狭めのう「SHIZUKU」ピアス
若狭めのう「SHIZUKU」ピアス BENICHU 微糖20°
BENICHU 微糖20° Obama Blue皿
Obama Blue皿







